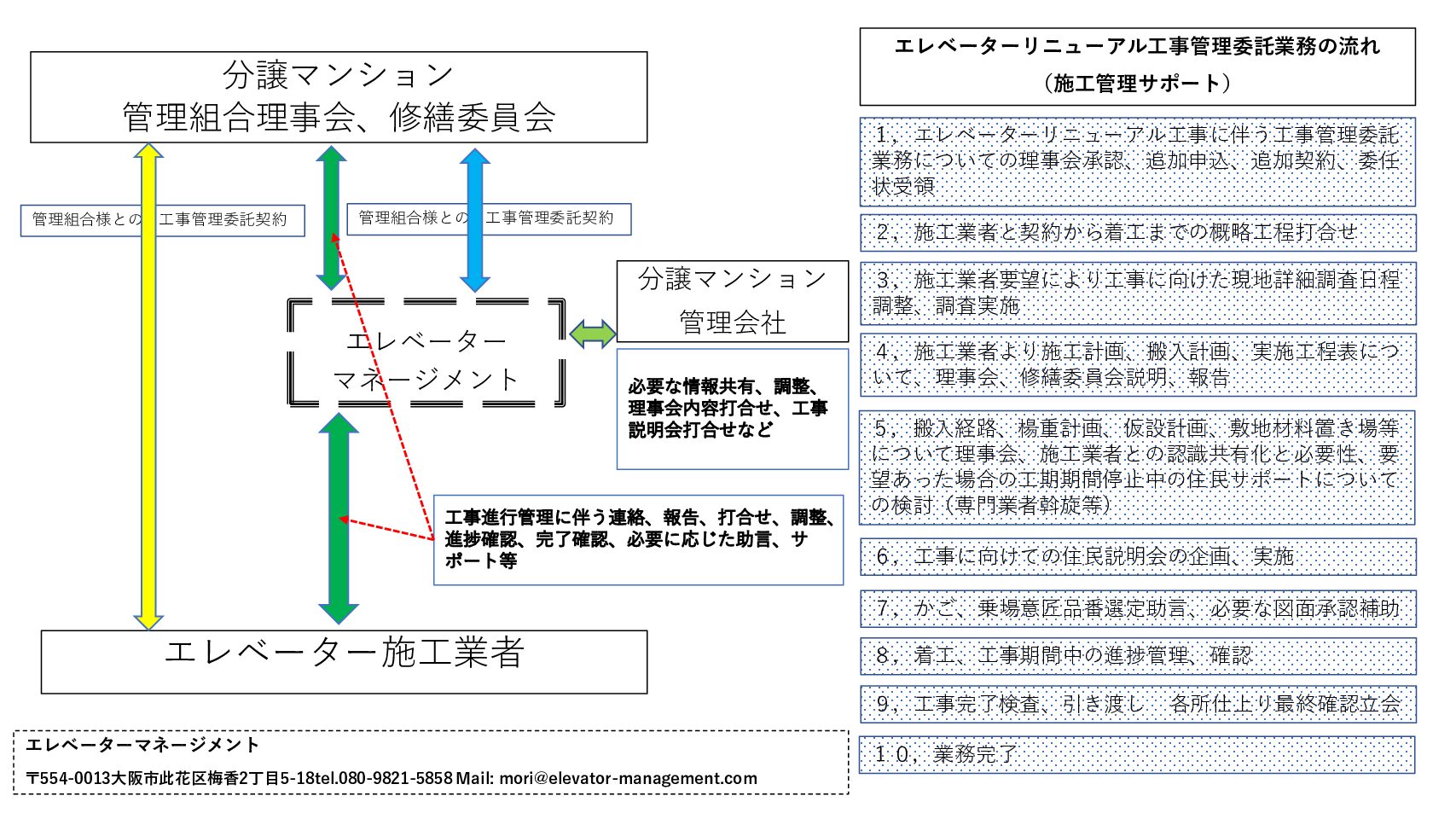マシンルームレス型開発・誕生はエレベーター史上最大の技術革新
現在の新築市場では、ほぼ国内設置の乗用一般型エレベーターはエレベーター専用の機械が設置される専用の機械室の無いタイプのマシンルームレス型のロープ式エレベーターとなっています。
世界で初めてエレベーターが誕生してから、現在まで170年経過しているのですが、エレベーターの構造が大きく変革したのはこのマシンルームレス型誕生が唯一ではないかと思われます。
世界、国内とぼぼ同時期にマシンルームレス型エレベーターが市場に導入が始まりましたが、3種類の構造のマシンルームレス型エレベーターが市場に投入されました。
一つは現在のように全く機械室がない訳ではなく、しかしながら従来の油圧式エレベーターのエレベーター機械室の約半分のスペースで設置できるリニア式エレベーターが市場に広く先駆導入されたと記憶しています。
動力を磁石の反発で起動させるので、ロープ式の巻上機、油圧式の油圧タンクや油圧ユニットも必要ありません。ただ、初期型のリニア式エレベーターは制御盤を昇降路内に収めるまでの省スペース化まで開発できなかったので、油圧式のように、1階の昇降路付近に制御盤のみが設置できるスペース確保の為、油圧式エレベーター機械室の約半分のスペースの専用スペース設置されていました。
それでも、設計者はいかに専用部、共用部の床面積スペースを確保できるか、1mm単位で建築設備を設計していましたので、当時としては画期的に受け取られ多くの建物に採用されていました。
2つめが、海外ヨーロッパで開発された小型薄型巻上機による構造のマシンルームレス型ロープ式エレベーターでした。
特徴は円形薄型のギアレス巻上機が昇降路最上部にレイアウトされ、巻上機、制御盤等のエレベーター関連機器すべてが、昇降路内に収められる構造で、この製品販売により一気にマシンルームレス型の普及が世間一般に広まったと言える状況でした。
3つめが、小型の巻上機を昇降路最下部ピットにアンカーで固定し昇降路内に薄型の制御盤を巻上機近くの1階フロア高さ位置にレイアウトされ、昇降路内にエレベーター設備機器を収めるタイプでした。
今現在は、リニア式エレベーターは生産、新規設置はされてなく、基本構造としては巻上機が昇降路上部か下部にあるタイプかの2種類のマシンルームレス型エレベーターが生産、販売、設置されています。

マシンルームレス型エレベーターのリニューアルに対する備え
マシンルームレス型エレベーターが国内設置してから約20数年が経過し、数社のメーカーが部品供給終了の案内が告知されています。
年内いっぱいと来年末までが一応の供給期限とされていますが、これに向けて該当機種対象のエレベーターに対して、リニューアルの検討案内がメーカー系、独立系保守会社から営業展開されていて、その件に関する相談がここ最近、急増している状況です。
私含め、エレベーター関係の業界人からすると、まだ市場にもっと古い旧式の機械室ありのロープ式エレベーターが多数、リニューアルを控えていてタダでさえ人手不足により、工事遅延や契約延期、さらには契約破棄といった話もでているのに、まだ、設置して20数年しかたっていないマシンルームレス型エレベーターの、リニューアルを営業するのだろうと理解できないのですが、メーカー各社の営業、製品開発の戦略によるものなのだろうと推察します。
いずれにしても、該当機種となった所有者は年内、来年末までに目途として制御関係のリニューアル工事を実施検討しなければなりません。
しかしながら、従来の機械室があるロープ式や油圧式と違ってリニューアル市場では、このマシンルームレス型エレベーターのリニューアルが一般市場化されていません。
独立系保守会社のこの構造に対するリニューアル製品開発が追いついていないのです。
先述したように、大きくメーカーによって昇降路内に巻上機の設置位置が昇降路最上部と最下部の2種類に分かれ、狭い昇降路内に制御盤、巻上機といった主要な機器を躯体に干渉することなく納めなければならないので、設計的要素の検討比率がかなり高いのです。
現在は部品供給終了機種はまだ、昇降路最下部設置のタイプだけとなっていますが、既存機器との互換性、レイアウトによる機器とのクリアランスの検証が必要となり、見積依頼を受けて作成するのにそういった設計技術検討無しでは見積もりがだせないのが現状です。
既存設置のメーカー系なら設計データーである躯体昇降路寸法、機器の取り合いが揃っているため、社内検討で見積もりがでますが、独立系保守会社がしかも、他社が保守契約しているエレベーターの見積となるとそういった現場機器の調査が必要なので、技術員を派遣して、各所の寸法を採寸して納まり、互換性を社内で持ち帰り設計検討しなければならず、時間と人件コストが見積もり時にかかってしまい、積極的に営業展開できない実情があります。
こちらとしては、見積を依頼するときの最低限の用意としては、エレベーター昇降路の建物竣工図面の提供が必須と言えます。
建物竣工時に建設会社、設計会社から施主事業者、管理会社へ引き渡される建物意匠竣工製本、エレベーターを新規設置される際に必ず建物と別途で昇降機の確認申請が為されます。その際の申請副本に綴じこまれているエレベーターの設計書、据付図、機器レイアウト図があればベストなので、依頼するまでにそういった関係図書を管理人室か集会室に保管されているであろう書庫、書棚を捜索して確保される事を推奨します。
まずは、見積依頼時にそういった図面は保管しているので情報提供できると伝えた上で、独立系保守会社は見積可否の返答をしてくるかと思われますのでご確認ください。
情報少なく、検討範囲が狭いので早期のご相談がベスト
部品供給期限が1,2年と迫っている中、競合環境の無い現時点での受注攻勢に営業戦略のポイントを置いていますので、そういった案内を受けられた所有者様は頭を悩まされていると心境をお察しします。
自ら、ネット検索で各エレベーター会社に依頼しても対応できるところが見つからずに弊社にご相談されるのですが、上記の見積に必要な条件を提示すると、検討可能となったり、国内大手の保守会社よりも地域密着の会社の方が開発スピードが速かったりと各々の環境状況によって様々な可能性があるので、出来るだけ検討段階に入ったならば早期にご相談ください。現場対象機器にあったベストな提案を心がけていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。